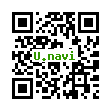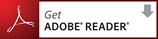授業内容・授業計画
| ポリシーとの関連 |
| ディプロマポリシー |
2 福祉や教育の従事者として必要な,福祉や教育の基本理念と専門的知識
3 児童障害福祉に関する専門的技能と心豊かな人間性に裏打ちされた優れた実践力 |
| カリキュラムポリシー |
4 専門ゼミナール |
|
| 授業のキーワード |
子ども主体の保育,地域子育て支援,現場演習,レポート作成 |
| 学生の到達目標 |
1.実際の生活の場にかかわりをもって,自ら問題意識を深める
2.個別の支援・指導を基本に,中間発表会等全体で集まる機会を適宜設ける |
| 授業の内容 |
授業は通期で行います。
第1回 オリエンテーション(修了研究の進め方)(目 標1,2)
第2回~第3回 一人ひとりの関心等について,意見交換し,課題設定について検討(目標1,2)
第4回~第33回 テーマに基づき,参観や資料収集に取り組む(目標1,2)
第34回 各自の研究課題の発表・協議(目標1,2)
第35回~第49回 関係資料の収集・文献研究(目標1,2)
第50回 中間発表(目標2)
第51回~第52回 論文の構成・体裁,執筆方法等について(目標1,2)
第53回~第57回 論文の加筆過程での相談支援(目標1,2)
第58回~第59回 論文の加筆・修正,論文の提出(目標1,2)
第60回 修了研究発表会(目標2) |
予習・復習の内容
(毎回90分程度) |
| 予習 |
第1回~第60回(共通)
テーマに基づき,参観や資料収集に取り組み,わかったことについてまとめておくこと。 |
| 復習 |
第1回~第60回(共通)
経過的指導を受けられるようにまとめておく。
また,指導を受けた内容についても,ポイントを整理し,論文に加筆・修正できるようにしておく。 |
| 展開 |
中間発表では,これまで研究の経過や明らかにしたい研究目的について明確にしておくこと。 |
|
| 成績評価 |
| 評価の基準 |
1.実際の生活の場にかかわりをもって,自ら問題意識を深めることができたか。
2.個別の支援・指導を基本に,中間発表会等で振り返りをしながら、自身の研究をさらに深めることができたか。 |
| 評価の方法 |
修了研究の過程における評価(30%)修了論文の内容における評価(60%)授業への参加意欲・態度(10%) |
|
| 教科書 |
教科書は用いない。必要な資料等を授業中に配布する。
|
| 推薦図書 |
|
| 参考URL |
|
| 備考 |
随時参考文献など紹介する |