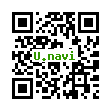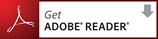授業内容・授業計画
| ポリシーとの関連 |
| ディプロマポリシー |
2 福祉や教育の従事者として必要な,福祉や教育の基本理念と専門的知識
3 児童障害福祉に関する専門的技能と心豊かな人間性に裏打ちされた優れた実践力 |
| カリキュラムポリシー |
2-9 教育実践に関する科目
2-11 特別支援教育の基礎理論に関する科目 |
|
| 授業のキーワード |
発達障害,LD,ADHD,自閉症スペクトラム,重複障害 |
| 学生の到達目標 |
1.発達障害,重複障害について基本的な内容を説明することができる
2.得た知識をもとに,障害のある子どもたちへの支援方法を考えることができる |
| 授業の内容 |
| 第1回 |
重複障害について~現場の実情と歴史的背景(目標1)
担当教員: 田所 明房 |
| 第2回 |
重複障害の教育課程と指導法~その1・肢体不自由・病弱等(目標1,2)
担当教員: 田所 明房 |
| 第3回 |
重複障害の教育課程と指導法~その2・知的障害・感覚障害等(目標1,2)
担当教員: 田所 明房 |
| 第4回 |
重複障害の子どもへの支援に必要なこと(目標1,2)
担当教員: 田所 明房 |
| 第5回 |
LDの理解と支援(目標1,2)
担当教員: 加藤 悦子 |
| 第6回 |
ADHDの理解と支援(目標1,2)
担当教員: 加藤 悦子 |
| 第7回 |
ASDの理解と支援(目標1,2)
担当教員: 加藤 悦子 |
| 第8回 |
園・学校の組織支援体制(目標1,2)
学習のまとめ(目標1,2) |
|
予習・復習の内容
(毎回90分程度) |
| 予習 |
第1回 1年次に学んだ障害関係の授業について復習をして授業に臨むこと。
第2回~8回 次回のテーマと主な内容についての予告に従って準備した上で授業に臨むこと。
|
| 復習 |
第1回~第8回 毎回の授業の資料とノートを見直し,教科書の関連の箇所で確認しておくこと |
| 展開 |
協議で出た意見については聞き流すことなくまとめておくこと。授業で学んだことと実習など現場で学んだことを関連づけて考えること。 |
|
| 成績評価 |
| 評価の基準 |
1.発達障害,重複障害等について基礎的な内容が理解できていること。
2.協議に積極的に参加し,的確に自分の考えを述べ,さらに深めることができていること。
|
| 評価の方法 |
発言・発表(30%)提出物(30%)定期試験(40%)
この比率は最終的に若干変更する可能性もある。 |
|
| 教科書 |
| 書籍名 |
見て分かる困り感に寄り添う支援の実際 |
| 著者名 |
佐藤 暁 |
| 出版社 |
学研 |
| 価格 |
1700円 |
| ISBN・ISSN |
ISBN,ISSN 4-05-403152-8 |
|
| 推薦図書 |
| 書籍名 |
LD ADHD &ASD(季刊誌) |
| 著者名 |
上野一彦 |
| 出版社 |
明治図書 |
| 価格 |
- |
| ISBN・ISSN |
- |
| 書籍名 |
特別支援教育研究(月刊誌) |
| 著者名 |
全日本特別支援教育研究連盟 |
| 出版社 |
東洋館出版 |
| 価格 |
- |
| ISBN・ISSN |
- |
| 書籍名 |
LD ADHD等関連用語集 |
| 著者名 |
日本LD学会 |
| 出版社 |
日本文化科学社 |
| 価格 |
1,190円 |
| ISBN・ISSN |
978-4-8210-7333-1 |
|
| 参考URL |
|
| 備考 |
|